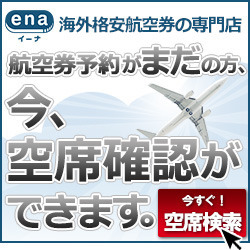気ままにぶらっと城跡への第24回目は、兵庫県佐用町にある三日月藩森家の陣屋です。
今回、当ブログで初めて陣屋を取り上げます。
陣屋とは、小藩の領主が構えた実質的な城のことですね。
そのため、天守や重層の櫓などを築くことができず、一つの曲輪しか置くことが許されていません。
館形式の建築物の陣屋しか築くことができない大名なのです。
それでも、中御門は立派な櫓門にしていますね。
三日月陣屋は、JR姫新線三日月駅から約15分のところにあります。
別称は乃井野(のいの)陣屋。
私は、2023年8月6日に攻城してきました。
*****************************

姫路駅から姫新線に乗り換え、龍野城のある本竜野駅から4つ目の駅三日月駅で下車です。
駅前から左に行き、酷暑のなか、途中からゆるい登り坂を山の方に歩くこと約15分で到着します。
駅前から、少し行くと左手の山腹にきれいに刈り込まれた三日月が見えました。
これは佐用町立三日月小学校の裏山ですね。

森忠政が開いた美作津山藩の森家は、元禄10年(1697)に後継ぎがなく改易となりました。
宗家森家の改易にともない、津山藩新田15,000石を領していた分家である森長俊が、領地を佐用・揖西(いっさい)・宍粟(しそう)3郡65カ村15,000石に移されたのです。
森長俊は、因幡街道と作州街道の要衝、佐用郡乃井野に陣屋を構えて三日月藩を立てます。
翌元禄11年に、森長俊は領地入り。
そして藩庁の陣屋と家臣屋敷の建設に着手し、元禄13年にはほぼ完成したようです。
乃井野地区はこのエリアの政治・文化の中心地として栄えました。
三日月藩森家は9代174年間続き明治を迎えます。
*****************************

御殿山の麓に陣屋を造り、三方を石垣で固め、志文川を外濠として、その間に武家屋敷を配しています。
絵図を見ると、よくわかりますよね。
防御に優れた形です。
志文川を渡って城下の入口は桝形なっており、大手筋をまっすぐ行くと両側に濠(池)を持つ表門があります。
武家屋敷の道は、城下町らしく折曲や食違があり、ところどころに門が配されていたようです。

表門は、西法寺に移築されていましたが、平成30年に本来の場所から少し位置をずらして復元されています。
小藩大名の陣屋表門は全国でも残存例が少なく、陣屋建築の実例として貴重な建物だそうです。
表門を真っ直ぐ進むと鍵の手になり、左に曲がりすぐに右折して進むと陣屋の前の広場に出ます。


左側に物見櫓、中央に中御門と、右側に通用門があり、長屋の前は水濠があり、橋が架かっています。
明治になって藩庁としての役割を終え、ほとんどの建物は解体されたのですが、物見櫓と長屋は小学校に移築され校舎として使用。
その後は公民館として使用されていました。

平成15年(2003)に物見櫓、長屋が元の場所に戻され、付属する中御門、通用御門、橋などが一体的に整備・復元されました。
整備にあたっては、古文書や絵図、発掘調査の成果などを元に、各分野の専門家の意見を取り入れ、「伝統的技術による文化財たり得る」(佐用町「三日月藩乃井野陣屋館」パンフレット)復元をめざしたものです。
中御門は、中央にあり陣屋では最も格式の高い楼門式の門で、藩主不在の時は閉められていたようです。
橋を渡って入った左側に番所が置かれていますよ。
2階には時打太鼓があり、城下町の門扉の開閉する合図や時を知らせていました。
立派な櫓門ですね。


物見櫓は三日月藩創建当初にはなかったとされていますが、三日月陣屋(乃井野陣屋)で唯一現存する江戸時代の遺構です。
2階の出格子窓からは旧武家屋敷地など、遠くまで見通せます。
現存する陣屋の物見櫓としては全国的にも希少なもの。
大変貴重な建築遺構として評価されているとのことです。
中御門と物見櫓の間にある幅約5mの建物が長屋ですね。
現在は、簡単な三日月藩や陣屋に関する展示室となっています。

瓦には、「天保14年(1839)卯十月瓦工三ケ月在平木是助源安綱作之」と書かれています。

なお、宗家の森家は無嗣断絶で津山の領地は召し上げられたのですが、津山2代藩主だった88歳の森長継(ながつぐ)によって助かっています。
森長継の長年にわたる奉公が賞され、徳川幕府から隠居料として備中西江原が与えられたうえに、森氏の存続と備中新見藩と播磨三日月藩の支藩の存続も許されたのですね。
宝永3年(1706)に、宗家の森長直(ながなお)は、備中西江原から播磨国赤穂藩に2万石で入封、赤穂藩藩主として12代160年余で明治を迎えています。
本能寺の変で信長に準じた森蘭丸は命を落としましたが、蘭丸の末弟の津山初代藩主である森忠政の森家は、明治まで存続しました。

5代藩主の快温(はやあつ)は儒学を重んじ、藩士子弟のために寛政9年(1797)に藩邸内に藩校「廣業館」を開設しました。
廣業館は、明治時代は廣業小学校として使用されていましたが、保存のためこの場所に移築された建物です。
この廣業館のとなりには、列祖(れっそ)神社があります。
列祖神社は、森家の祖、美濃国金山城主・森可成(よしなり)、津山藩祖・森忠政、三日月藩祖・森長俊の三霊を祭る神社です。
江戸時代は、現在の東京都目黒区にあった三日月藩邸に祀られていたのですが、明治3年に当地に社殿がつくられました。
現在残っている「旧三日月藩郭内図」はこの神社に奉納されたものです。
▼関連記事

三方里山をぐるっと回って三日月小学校の西側にある「味わいの里三日月」を、陣屋の管理をされていた方に教えていただきました。
農産物や特産品の販売とそば処があり、遅い昼食をとりました。
蕎麦は細めでしっかりとした歯ごたえがあり、美味しかったです。
三日月駅の周辺で食事ができるところはここだけでした。
三日月駅まで約10分程度のところにありますよ。
三日月の地は、芭蕉の「三日月や地はおぼろなる蕎麦畠」という句碑が江戸時代に建てられたという、蕎麦で有名な処でした。
(写真は筆者撮影)
*三日月陣屋詳細(三日月藩乃井野陣屋館)
・営業時間:土曜日・日曜日・祝日 / 10時から16時まで
・休業日:平日と年末年始
・入館料:無料
・電話:0790-79-3002(開館日のみ)
▼PR
▶【じゃらん】国内25,000軒の宿をネットで予約OK!2%ポイント還元! ![]()
【参考文献】
佐用町ホームページ「三日月藩乃井野陣屋館」、佐用町「三日月藩乃井野陣屋
館」(パンフレット)、『別冊歴史読本 71 城郭研究最前線 ここまで見えた
城の実像』(新人物往来社 1996年10月25日発行)、『別冊歴史読本 江戸三
百藩 藩主総覧』1997年8月号(新人物往来社 1997年8月26日発行)他
▼PR
▼PR 宅配デリ