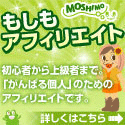*岩国城とは?
岩国城は、毛利家領国の東の要衝の地に築かれています。
錦川を望む標高約200mの急峻な横山の山頂に築かれた要の城ですね。
「日本100名城」(第74番)に選定されており、別称は横山城。
岩国城へは、1997年7月12日に登城しました。
*岩国城の歴史(築城から廃城まで)

関ケ原の戦いに敗れた西軍の大将・毛利輝元(てるもと)は、それまで8カ国の大大名でした。
しかし負けたため、周防(すおう)と長門(ながと)の二カ国に削封。
そのとき毛利輝元の孫にあたる吉川広家(きっかわ ひろいえ)も、出雲の月山富田(がっさんとだ)城12万石の城主から岩国3万石の領主に転封となっています。
▼関連記事
広家は、翌6年から山陽道の東の要衝の地・岩国に、領国防備と毛利家への忠誠のため城と城下町の建設に取りかかります。
岩国城は、横山の山上の城郭(山城)部分と、その南麓の御土居(おどい 居館)部分の2パートで構成。
初めに建造したのは、下の図の一番下、紺色(濠)で囲まれた御土居です。

陣屋とは言えない、城郭のような居館でした。
- 背後は山
- 正面と両側面は水濠
- 正面の中央に内桝形門の櫓門
- 東西隅に二重櫓
- 西の奥に物見櫓
これらで固められていたのです。
この御土居を中心にして武家屋敷が立ち並び、錦川が外濠の役割を果たしています。
山頂の城郭は、本丸の桃山風の天守を中心に二の丸・北の丸・水の手を設けていました。
そして、山城の大手櫓門と要所に櫓を設置。
水の手曲輪には大釣井、小釣井、清水の三井戸と櫓が二基ありました。
連郭式の縄張りです。
各曲輪のまわりに石垣を築き、本丸と北の丸の間には空堀が掘られた厳重な守りの城郭でした。
しかし、岩国城天守は、毛利家の本城・萩城の支城扱いだったのですね。
そのため元和元年(1615)の一国一城令により、天守をはじめ山頂の建物や石垣はことごとく壊されてしまいます。
竣工わずか7年のことでした。
それ以後、岩国城は城郭のない居館だけの城となってしまいました。
吉川氏の不幸はそれだけではありません。
関ケ原の戦いで主家である毛利氏が西軍の総大将となりましたが、広家は西軍の味方をしませんでした。
それは、家康と密約を結んでいたため。
東軍が勝ったあとも、密約が活きて吉川家は取り潰されませんでした。
ただし主家である毛利家は、取り潰しが危ぶまれます。
このとき広家は「主家をつぶして吉川家だけが恩顧を受けることは出来ない」と毛利家の存続を家康に嘆願し、家康に聞き入れられたそうです。
毛利家は防長二国に大きく削減されましたが、広家によって改易を免れました。
しかし、毛利家は広家を主家に背いたものとして扱い、岩国藩創設の申請をしませんでした。
岩国藩の創設を家康は認めていたにも関わらずです。
そのため吉川家は城持ち大名だったのですが、扱いは毛利家の家臣。
岩国城の山頂の城郭部分は取り壊され、城を持つことが許されなかったのですね。
岩国は幕末まで正式の藩とは認められていません。
吉川家が、藩主として認められ城持ち大名となったのは、なんと明治元年(1868)のことでした。
しかしそのときすでに、最後の藩主は死亡。
岩国藩は明治4年の廃藩置県により廃藩となったため、正式に独立した藩としてはわずかな期間だったのですね。
歴代の城主は、産業の振興、人材の育成、文化の向上に努めました。
広家の入国当初は3万石でしたが、寛永年間(1624~44)には6万石、幕末には実質10万石になっていたと言われています。
吉川家歴代の歩みがこの発展ぶりからもわかりますよね。
終戦後いち早く市民あげての天守復興運動が盛り上がりますが、それは吉川氏のそれまでの徳政の結果でしょう。
また人々の岩国を愛する心の現れとも言えますね。
*岩国城|現存する遺構・見どころ

昭和37年(1962)に、古図面をもとに鉄筋コンクリートで外観復元された天守です。
平櫓を付けた望楼型複合式天守ですね。
天守は四重六階建て。
三重目が二階に区切られ、しかも三重目上階が下階よりも大きく張り出しています。
また三重目の上に望楼が乗る形をしていて、この望楼が大入母屋に乗る方形の支柱面より大きく四方に張り出しています。
すなわち、四階部分が張り出す形、独特の構造をした天守です。
こういった天守の形は、「南蛮造り(なんばんづくり)」とか「唐造り(からづくり)」と呼ばれています。
四重の屋根に千鳥破風が据えられ、その下には四方に華灯窓が設置。
張り出している4階を支える方杖(ほうづえ)の一種、「ありこし」の形を見る
ができます。
最上階も少し張り出しています。
張り出した部分とその上下だけが白漆喰総塗籠ですが、その他は黒い板張りです。
本当に、独特の姿をした天守ですよね。
再建された天守は本来のところではなく、市街地から見えるように位置をずらして本丸南隅に建てられました。
天守内部は博物館となり、吉川家ゆかりの資料が展示されています。
本来の天守台も、平成8年に発掘調査をして復元されていますよ。



本丸や北の丸で見られる壊された石垣などは、岩国城に残された歴史の爪痕です。
*******************************




*岩国城の周囲の観光情報


今では岩国の観光名所となっている錦帯橋は、他に類例のないアーチ型五連の木橋です。
この錦帯橋は山麓の居館部分と対岸の城下町を結ぶため、延宝元年(1673)に三代藩主広嘉(ひろよし)の代に建設されました。
岩国城の大手門の役割を果たしています。
城下町を流れる錦川には、それまで何度も橋が架けられましたが、橋は洪水の度に流されてしまいます。
流されない橋をどうしたら造ることが出来るのか悩んでいた広嘉は、中国の本に載っている庭園のアーチ型の石橋を見て思いつきます。
川床を敷石で固め、水中に四つの島を築いて橋台とし、その島伝いに五つの反橋を架けたのです。
木造部分は何度か崩壊・流出したのですが、橋台の部分は現在までほとんど無傷のままで残っています。
江戸時代には、この橋の両側に番所があり、通行を制限していたということです。

吉川英治の『宮本武蔵』では、宮本武蔵の宿敵である佐々木小次郎は岩国生まれ。
錦帯橋畔の柳や燕を相手に「燕返し」を編み出したとされています。

明治18年(1885)には居館跡に、藩祖・吉川元春ほか吉川家歴代を祀る吉香(きっこう)神社を遷座し公園としました。
錦雲閣は、その時吉香神社の絵馬堂として建てられました。
旧南矢倉跡に建てられたためか、外観は二重櫓ですね。



私が岩国城を探訪したときは、岩国国際観光ホテルに泊まりました。
錦川のすぐ前のホテルです。
郷土料理の岩国寿司を食べてから、夜には前の鏡川で夏の風物詩「鵜飼い」を楽しみました。
それと日本で唯一天然記念物の白蛇も見てきました。
2012年には岩国白蛇神社が建立され、白蛇の石像と飼育場があるとのことです。
*岩国城詳細
・住所:山口県岩国市横山3丁目
・アクセス:岩徳線川西駅から徒歩20分、さらにロープウエーで3分。ロープウエー下車後、徒歩10分
・営業時間:9:00~16:45
・休業日:岩国城ロープウエー点検日
▼PR
【参考文献】
平井 聖監『城 6 中国 甍きらめく西国の城塞』(毎日新聞社 平成8年11月25日発行)、日本城郭協会監修『日本100名城 公式ガイドブック』(学習研究社 2007年7月3日第1刷発行)、南條範夫監修『日本の城 名城探訪ガイド』(日本通信教育連盟)、『城と城下町 西の旅』(日本通信教育連盟)、『城 其ノ参』及び『城 解説編』(日本通信教育連盟)、石井進監修『文化財探訪クラブ 城と城下町』(山川出版社 1999年7月25日1版1刷発行)、西ヶ谷恭弘編『国別 城郭・陣屋・要害・台場事典』(東京堂出版 2002年7月15日初版発行)、全国城郭管理者協議会監修『復元イラストと古絵図で見る日本の名城』(碧水社 1995年4月18日第一刷発行)他
▼PR
▼PR