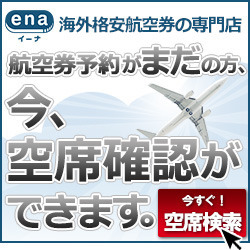琵琶湖畔の小高い丘にある平山城で、別称は金亀城(こんき)城。
2006年に「日本100名城」(第50番)に選定された、国宝です。
現在は国宝なのですが、なぜか戦前の旧国宝保存法による国宝には指定されませんでした。
それは彦根城天守が大津城天守の移築天守だったからではないかと、私は思っています。
▼関連記事
ではまず、歴史から参りましょう。
徳川四天王の一人の井伊直政(いい なおまさ)は、関ヶ原の戦いのあと論功行賞により6万石を加増され、上州高崎から18万石の城主として、石田三成の佐和山城に入城しました。
しかし山城で不便な佐和山城ではなく、新たな支配の拠点として近世城郭を築こうとしたのですね。
ところが残念ながら、直政は戦傷を悪化させ死去。
直継(のちの直勝 なおかつ)は父の直政の遺志を受け継ぎ、慶長8年(1603)、標高136mの彦根山に築城に着手します。
大坂の豊臣家や西国大名に備える戦略的要素を帯びた城として、徳川幕府の全面的支援を得ての築城となりました。
そのため佐和山城や大津城、長浜城など周辺の城から用材や石材などを調達して進められ、3年後に天守が完成します。
彦根城を紹介するテレビ番組では、彦根城を今風に「リサイクル城」といっていましたが、そういわれればそうだよね、と納得しました。
琵琶湖を一望する鉄壁の要塞ですが、城郭のまとまった美しさを伝える数少ない城です。
江戸時代を通じて一度も移封されることなく井伊氏14代の居城として存続、明治を迎えます。
珍しいですね……14代が同じ城を守ったとは。
****************************
彦根城へは1997年8月5日に登城しました。

平山城ですが、彦根城は山麓の居館(表御殿)と彦根(金亀)山頂に構えられた詰城から構成されていて、詰と居館という分離型は戦国期の山城構造そのものです。
また後にも述べますが、山城特有と言っていいようなさまざまな防御をしています。
城郭は、西は琵琶湖、北は内湖、東から南へ芹川の流れで囲った総構え。
幾重にも濠を巡らせた城郭でした。
本丸を中心に西の丸、出曲輪、観音台、山崎曲輪、太鼓丸、鐘の丸を左右に配し、山麓には表御殿があります。
西の丸には三重櫓(重要文化財)が遺構として現存しています。
天守台は牛蒡積みで野面積みの石垣。
その上に、切妻破風、千鳥破風、金箔押し飾り金具付きの軒唐破風などのいろいろな破風とたくさんの華頭窓が美しく組み合わされ、三重目には装飾的に廻り縁が付けられた天守が載っています。


同じ国宝の姫路城や犬山城、松江城とは明らかに趣の異なるいかにも桃山風の優美さのある天守ですね。
現存天守は、大津城の四重五階天守を三重に縮めて移築したものであることが、解体修理の結果明らかになっています。
また現存天守のなかでは、建築年代が確かめられる最も古い遺構の天守です。
ちなみに1878年(明治11年)に解体される予定でしたが、大隈重信が「武士の魂の入れ物」と言ったそうで、保存されることになりました。
鶴の一声……。


廊下橋の下は堀切で表門口からの道と大手門口からの道が出会うようになっていて、敵を惑わす複雑な防御構造が彦根城の特色とも言えます。
近世の山城では、こうした堀切を尾根の途中ではなく曲輪間に設ける事例は、ほとんどありません。
わずかに大分県の豊後佐伯城ぐらいです。
こうした堀切の存在も戦国期の山城でしょう。
この廊下橋を渡らないと本丸には入れないので、いざという時には切り落とします。
廊下橋を渡って天秤櫓をくぐり、本丸へ。
廊下橋を中心として天秤のように左右に二重櫓を構える形から天秤櫓(重要文化財)と言われ、長浜城の大手門を移築したと伝わっています。
太鼓丸の急角度の道を曲がると、目の前には一重櫓門が。
本丸入口を固める太鼓門櫓と続櫓(重要文化財)で、佐和山城からの移築と推定されています。

なお、山頂から山麓にかけて五本もの石垣が縦方向に巡らされ攻城側の斜面移動を阻止しています。
これは登り石垣(竪石垣 たていしがき)と呼ばれ山城に見られるものですが、彦根城では竪堀とも併用されていました。
このような竪石垣は、全国的にも松山城など数例しか見られない貴重な遺構です。

内濠の石垣は二重です。
このように上部に石垣を用い、その下を土塁としているものを「鉢巻石垣」と呼んでいます。
また、土塁の下部に石垣が用いられている石垣は「腰巻石垣」です。
彦根城には高い立派な石垣が多くありません。
これは井伊氏が東国出身であり、幕府普請の助役大名も石垣普請が得意ではなかったことが原因でしょう。
彦根城では、腰巻石垣や鉢巻石垣が多用されたと考えられています。
西国の城郭では珍しい構造です。

***************************

近江八景の縮景を池畔に再現した回遊式庭園です。
鳳翔台(ほうしょうだい)の数寄屋の上に、天守を望む素晴らしい景観が彦根城訪問の楽しみのひとつ。
隣には旧藩主の下屋敷・楽々園があります。
そして、彦根城博物館は、彦根藩の藩庁であった表御殿を昭和62年に復元したものです。
常設展示では、彦根藩主井伊家に伝わる甲冑などの大名道具を中心としたものが展示されていますよ。
ちなみに、観光のモデルコースとしては以下の通りです。
旧鈴木家長屋門
↓
いろは松
↓
埋木舎(うもれぎのや)
↓
↓
二の丸佐和口多聞櫓(写真①)
↓
馬屋
↓
脇家屋敷長屋門
↓
表御殿(彦根城博物館)
↓
鐘の丸
↓
天秤櫓(写真③)
↓
時報鐘
↓
太鼓門櫓(写真参照④)
↓
天守(写真②)
↓
西の丸三重櫓
↓
玄宮楽々園(写真⑤)
↓
旧西郷屋敷長屋門
全部で2時間程度でしょうかね。
よい散歩になりますよ。
人気のゆるキャラ「ひこにゃん」にもどこかで会えるかもしれません。
最後に、天守からの琵琶湖の素晴らしい眺めをのせておきますね。

*彦根城詳細
アクセス:JR彦根駅から徒歩で約15分/彦根ICから車で約15分
営業時間:8時30分~17時
休業日:年中無休
【参考文献】
平井 聖監修『城 5 近畿 華と競う王者の城』(毎日新聞社 平成8年9月25日発行)、財団法人日本城郭協会監修『日本100名城公式ガイドブック』(学習研究社 2007年7月3日第1刷発行)、中井均監修『超雑学 読んだら話したくなる 日本の城』(日本実業出版社 2010年6月20日発行)他
▼PR
▼PR