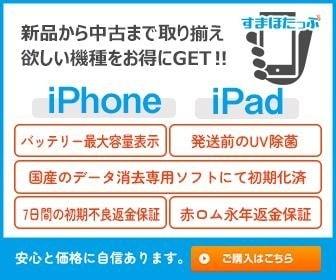▼PR

北海道の五稜郭ですね。
24回目は、桜の名所としても特に有名なこちらの紹介です。
そのため、厳密には城とは言えません。
しかし、戦闘を前提とした防御施設ですので、2006年に日本100名城(第2番)として選定されていますね。
幕末期の近世城郭最後の城です。
正式名称は亀田御役所土塁(かめだおやくしょどるい)ですが、一般には五稜郭(ごりょうかく)と呼ばれていて、そっちの通称の方が有名です。
五稜郭は、日米和親条約により開港となった箱館(函館)を、外国からの攻撃に備えることと蝦夷地経営の目的で、函館市の北部亀田川の東側に徳川幕府によって築城されました。
西洋軍学や築城術に優れた伊予(松山)大洲出身の蘭学者武田斐三郎(あやさぶろう)が設計を担当。
8年がかりで元治元年(1864)に完成の星形(稜堡式)をした、ヨーロッパ式城郭です。

周囲350mの星形の曲輪の上に土塁(実際には石垣)を築き、五つの稜に砲座を設けて(実際には火砲は設置されなかったようです)周囲を濠で囲む形の城郭です。
***********************
五稜郭への初登城は2002年6月30日です。
2006年には、松前城が攻撃される前に江刺の奥に築城した館城址と函館空港のすぐ隣にある志苔館跡(しのりだて 続日本100名城第101番に登録)と三城址を探訪しました。
志苔館跡はアイヌと和人が戦った道南十二館の一つで立派な土塁が残っていますが、大雨と強風で大変な目に合いました。
どこに出しても恥ずかしくない雨男ですー。特技はハリケーンを呼ぶこと!
稜堡式の城は15世紀にヨーロッパで考案された城の形で、防御に死角がありません。
五角形の堡頭に砲座を築き、敵に十字砲火を浴びせられるようにしたものです。
城壁は大砲の衝撃に強い土塁の予定でしたが、冬は凍土となるため計画を変更し石垣にしたようです。
しかし、稜堡式の城郭には多くの兵士と多量の弾薬が必要ですよね。
和式の城郭は敵からの攻撃を数方向に限定して、少ない兵力でそこを徹底的に守る考え方で縄張りをしますが、この稜堡式城郭はそんな考えはありません。
私は机上の防御理論だと思います。
石垣の最上部には敵の侵入を防ぐ為、庇のような刎出(はねだし)が造られています。


↑↑のような馬出用堡塁(半月堡)をすべての方向の5ヶ所に造る予定でしたが、財政難のため1か所となりました(お金ないのは辛い)。
曲輪の中央に望楼付きの庁舎と付属施設がつくられ、箱館奉行の中央施設箱館奉行所として慶応3年(1867)まで徳川幕府が管理していました。

明治維新後、新政府はここを箱館裁判所とし、後に「箱館府」と改称。
しかし明治元年(1868)の10月26日、軍艦八隻とともに江戸を脱走してきた榎本武揚(えのもと たけあき)ら旧幕臣に占領されてしまいます。
「蝦夷共和国」の樹立を宣言した榎本武揚と旧幕府脱走軍が籠城。
明治元年から翌年にかけて苛烈な戦闘を繰り広げ、明治2年に長州藩兵を中心とした新政府軍は松前城を奪還します。
そして元新選組の土方歳三(ひじかた としぞう)らが、必死の抵抗をつづける五稜郭を攻撃します。
苛烈な戦闘を繰り広げた「箱館戦争」と呼ばれる激戦の末、5月18日榎本は五稜郭を開城し、官軍に下ります。
五稜郭は外国との戦いの為に築城されましたが、皮肉にも国内戦の戦場となりました。
ちなみに榎本は、この後2年半ほど獄に繋がれていました。
しかし明治新政府の逓信、文部、外務、農商務省の各大臣を務めて、明治41年(1902)に73歳で没しています。
薩長閥の新政府のなかにあって、もと賊軍の総裁である榎本のこの出世は驚きです。
それ程の稀有な人材だったのでしょうね。
この奉行所は、私が探訪した時は残念ながら復元されておりませんでした。
規模はほぼ三分の一となりましたが、平成22年(2010)7月に木造復元されオープンしています。
五稜郭タワーが創業40周年事業の一環として土方歳三のブロンズ像を制作し、五稜郭タワーにそれを建立。
彫刻家・小寺眞知子氏が制作しました。
新選組副長の像はこのほかに、歳三の座像、胸像があります。

五稜郭タワーは平成18年(2006)に開業した2代目(避雷針高さ107m)で、初代のタワー(高さ60m)は昭和39年(1964)の五稜郭築造100年目を記念して開業しました。
展望台から五稜郭の台地に輝く星型の眺望はもちろんですが、函館山や津軽海峡などの眺望を楽しむことができますよ。
必見です。

五稜郭探訪の後、タクシーで15分ほど(北東5km)の高台のところにある、四稜郭という未完成の城址を訪ねました。
ほとんどの人に知られておらず、あるのは土塁だけです。

四稜郭は「函館戦争」のときに蝦夷共和国が築城した堡塁。
五稜郭をサポートする支城として作られましたが、井戸などの設備はなく野戦築城に近かったようです。
昭和9年(1934)に国の史跡に指定されています。
5月には付近がすずらんの花畑となるそうなので、五稜郭に行く際にはこちらにも足を伸ばしてみてくださいね。
*五稜郭詳細
アクセス:函館市電2系統、5系統「五稜郭公園前駅」徒歩15分/函館駅前より函館バス106ループ系統「中央図書館前」下車
営業時間:5:00~19:00(11月~3月:18:00)
休業日:年中無休
【参考文献】
平井 聖監修『城 1 北海道 東北 吹雪舞うみちのくの堅城』(毎日新聞社 平成9年3月25日発行)、財団法人日本城郭協会監修『日本100名城公式ガイドブック』(学習研究社 2007年7月3日第1刷発行)、中井均監修『超雑学 読んだら話したくなる 日本の城』(日本実業出版社 2010年6月20日発行)、『城と城下町』(日本通信教育連盟)「市立函館博物館五稜郭分館」パンフレット他
▼PR